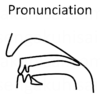【目次】 [close]
幼児期(0~6歳)の話し言葉(言語表出)
言葉の成長において幼児期という時期は非常に変化が著しい時期です。
幼児期前半、とりわけ単語が出始めて文章に移行する1歳~2あるいは3歳の時期は言葉の量の変化に大人の注目がいきがちです。
一方で、幼児期後半、4歳以降は話す言葉の質がより変化していきます。
相手の話を聞いてから自分の話をするという会話の「間」の取り方。
保育園の事情を知っているお母さんには話題を端折って話、仕事で事情を知らなかったお父さんには説明を多めに入れるといった相手に応じて話す内容を取捨選択する。
言葉が成長していき6歳頃、つまり小学校にあがる直前頃にはこういった言葉のキャッチボールが一通り完成してきます。
年齢別の発達の特徴と目安
およそ0歳頃
0歳頃は言葉というよりは「あー」「うー」など母音の音、「ぱ」「ま」など唇をつける音。
言葉を話す土台として、母音を中心とした音を人に向けて発することを覚える時期です。
およそ1歳頃
1歳前後になると「ママ」「パパ」など単語を話し始める傾向があります。
およそ2歳頃
そして2歳頃になるとずいぶんと言葉のバリエーションが増えてきます。
- 2語文が出る
- 2語文の復唱
- 言える動詞がでてくる
- 「おいしいね~」など共感的な言葉が言える
- 「ばいばい」や「ちょうだい」、「だっこ」など言える
- 「ここ」「これ」などが言える
- 「なに」「どれ」などが言える
- 名前を聞かれたら、フルネームで答える
- 対の形容詞を言える
- 「名詞+動詞」の表現
などです。
およそ3歳頃
- 4色くらい色の名前を言える
- 2~3語文を真似て言える
- 「コップは飲むときに使う」など簡単な物の説明ができる
- 反対語を言える
およそ4歳頃
- いろいろな色の名前が言える
- 「~のつく言葉」が、言える
- 空間概念を表わす言葉が言える
- 幼児語が減る
- 両親の名前が言える
およそ5歳頃
話す文章が長くなるだけでなく、抽象的な概念も身についてきます。
- 理由が言える
- 動詞の使い分け
- 特徴から対象を推測する
- 曜日が7つ言える
- 数字を逆から言う
およそ6歳頃
そして6歳児の言語表出の特徴としては、
簡単ではありますが論理的な表現ができはじめます。
おわりに
子供の発達には個人差があります。
医学的・発達心理学的には上記のように年齢ごとに発達の傾向が明らかにはなっていますが、
必ずしも発達の目安に個人を当てはめる必要はないでしょう。
発達のペースは人それぞれですから、逐一一般的な目安に当てはまるわけではありません。
発達がゆっくりな時期もあれば急速な時期もあります。
大切なのはその子自身が今どのような発達段階でどのような刺激を必要としているのかということです。
その他の記事
参考資料
『遠城寺式乳幼児分析的発達検査法について』(認知神経科学会)2023年3月18日閲覧