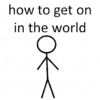前のページ
前のページにて、ソーシャルスキルトレーニング(SST)について簡単に見ていきました。
このページではより専門的な知識も交えてソーシャルスキルトレーニング(SST)を見ていきます。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)の概要
ソーシャルスキルトレーニング(SST)は効果的な対人コミュニケーションを学ぶことであり、方法としては5段階のコーチング法を用いることが多いです。
専門機関で実施されることが多いですが、近年は教育現場で行われることも増えてきています。
指導内容としては言葉かけや話の聞き方などを扱うことが比較的多いですが、いずれにせよ学んだスキルを実生活でも行う「般化・維持」を積極的に促進することが重要です。
解説
ソーシャルスキルトレーニングとは
そもそも 「ソーシャルスキル」とは「効果的な対人コミュニケーションに必要な言語的および非言語的行動」と考えられます。
つまりソーシャルスキルトレーニングとは、人間関係・社会生活をより円滑にうまくやっていくためのスキルと言えるでしょう。
自閉症スペクトラム障害(ASD)をはじめとする発達障害児(あるいはそういった特性が比較的高い子)は、ソーシャルスキルに苦手さを示す場合があります。
一方で、ソーシャルスキルは学習を通して獲得されることも示唆されており、介入の重要性がうかがえます。
指導方法
国内で行われているソーシャルスキルトレーニングのほとんどは5段階のコーチング法が用いられています。
この5段階とは「言語的教示」「モデリング」「行動リハーサル」「フィードバック」「般化」となります。
つまり、練習するソーシャルスキルについて説明し、見本を示し、やってみて、その様子をあとから話し合い、普段からもできるよう実生活に導入していくということです。
指導内容・例
当然ながら、ソーシャルスキルトレーニングの内容の選定にはアセスメント(評価)が重要です。
これを前提とした上で、練習対象によく挙がるものは、「あたたかい言葉かけ」や「上手な話の聴き方」などがあります。
また、ソーシャルスキルトレーニングは般化・維持が難しい面もあり、これらを促進する積極的な取り組みが必要となります。
家庭での練習(宿題)や訓練終了後の定期的なソーシャルスキルの評価は取り組みの一例と言えます。
参考資料
半田健(2019)『日本における自閉スペクトラム症児を対象としたソーシャルスキルトレーニングに関する研究動向』(一般社団法人 日本LD学会)2025年8月26日閲覧
『ソーシャルスキルトレーニング絵カード』(エスコアール)2025年7月26日閲覧